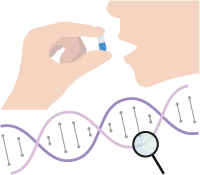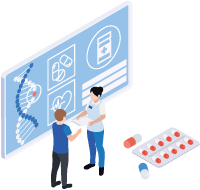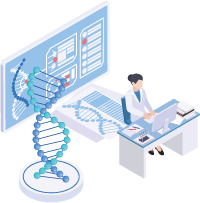薬剤反応性の体質を調べる検査です
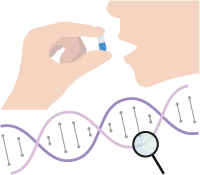
薬に対する反応性には個人差があり、標準用量を使っても人によって効きめが違うことや副作用が現れること、また特定の薬に対してアレルギー反応を起こすことがあります。
個人差の原因はいろいろありますが、そのひとつとして生まれつきの体質が関連していることが知られています。薬剤反応性の体質は遺伝子を調べることによって推定することができます。
検査を受けるメリット
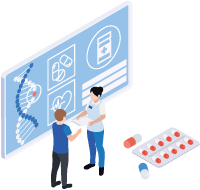
ご自身の薬剤反応性の体質を知ることができ、これは以下のメリットがあります。
- 効かない薬を避けることができます。
- 体質的に副作用リスクの高い薬を避けることができます。
- 薬剤アレルギーを未然に防ぐことができます。
よって、安全で安心な薬物治療を受けることができます。
遺伝子情報は一生変わりません。一回の検査で調べた結果を生涯使うことができます。
よって、現在投薬治療中の方に限らず、健康な方でも未病のうちに調べておくことによって、将来において安心・安全な薬物治療を受けることができます。
検査結果の活用法
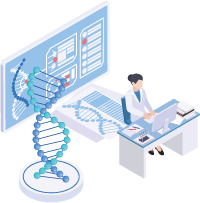
医誠会国際総合病院ではゲノム薬理学検査の結果を厳重に保管・管理し、当院での診療に活用します。検査を受けられた方が当院で薬物治療を受ける場合、処方される薬剤に関して薬剤反応性遺伝子情報と照合し、その方の体質に合うように有効かつ安全な薬剤と用量を選んで処方します。
検査結果は当院の専門スタッフがご説明し、検査結果報告書をお渡ししますので、他の医療機関における診療にもお使いいただけます。
より詳しい情報を知りたい方へ
- この検査では、日本臨床薬理学会の推奨、国際ガイドライン(Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC®))等、医薬品添付文書等に基づき、医学エビデンスが確立した20遺伝子を検査対象としています。
- 検査対象は生殖細胞系列の薬剤反応性や薬物動態関連遺伝子であり、がん遺伝子は対象としません。
- 薬物代謝酵素、薬物トランスポーター、HLAなどの遺伝子を対象とし、日本人における主要なバリアントを検査します。具体的な検査項目を末尾に示します。
- 医師の指示ではなく、個人の自由意思で受ける自費の検査(いわば「ゲノム健診」)です。保険診療ではありません。
- 全ての薬に対応しているわけではありません。現時点では、主に日本臨床薬理学会が推奨する約40種類の薬を対象としていますが、今後、医学研究の進展に応じて増やしていく予定です。
[現在の対象薬]
- 抗凝固療法に用いるクロピドグレルやワルファリン
- 高コレステロール血症の治療に用いるスタチン
- けいれん治療に用いるカルバマゼピンやフェニトイン
- 感染症治療に用いるペニシリンやアミノ配糖体
など
検査対象の遺伝子
- CYP (Cytochrome P450)2A6, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A5
- DPYD (dihydropyrimidine dehydrogenase)
- NAT2 (N-acetyltransferase 2)
- NUDT15 (Nudixhydrolase 15)
- TPMT (Thiopurine S-methyltransferase)
- UGT1A1 (Uridine diphosphate glucuronosyltransferase 1A1)
- SLCO1B1 (solute carrier organic anion transporter family member 1B1)
- ABCG2 (ATP-binding cassette subfamily G member 2)
- VKORC1 (vitamin K epoxide reductase complex subunit 1)
- HLA-A, HLA-B, HLA-DRB1, HLA-DQA1
- ミトコンドリア遺伝子変異 A1555G, C1494T