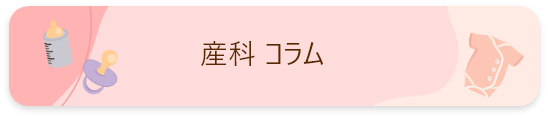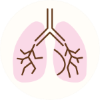婦人科
月経に関するお悩みや尿トラブル、妊娠・不妊のご相談、子宮や卵巣の病気、性感染症、更年期障害など、幅広いお悩みに対応しています。 問診・内診・超音波検査・子宮がん検診(基本的な検査)などを通じて、女性に多い病気の早期発見と適切な治療を行います。 生理不順や不正出血、月経前の不調、イライラ感、更年期に伴う体調変化などでお困りの方はお気軽にご相談ください。
医誠会国際総合病院 婦人科月経不順
月経とは、通常およそ1か月ごとの周期で起こり、数日間で自然に止まる子宮内膜からの出血を指します。このリズムから外れた状態を「月経不順」と呼びます。 原因はさまざまで、ストレスやホルモンバランスの乱れ、疾患が関係していることもあります。周期に乱れがある場合は、婦人科を受診されることをおすすめします。
月経困難症
月経に伴うつらい症状を「月経困難症」といい、原因によって2つのタイプに分けられます。
「器質性月経困難症」は、子宮筋腫、子宮腺筋症、子宮内膜症、子宮の形の異常など、何らかの病気が原因で起こるものです。
「機能性月経困難症」は、特に目立った病気がないにもかかわらず痛みなどの症状が現れるタイプで、多くの方はこちらに当てはまります。
症状は下腹部の痛みだけでなく、頭痛、吐き気、気分の落ち込みなどさまざまです。
月経前症候群(PMS)
月経前の3~10日間に現れ、月経が始まると自然に軽快・消失する心身の不調です。 身体的な症状には、腹痛、頭痛、腰痛、むくみ、お腹や乳房の張りなどがあり、精神的な症状としては、気分の落ち込み、イライラ、眠気や集中力の低下、倦怠感、睡眠トラブルなどが挙げられます。これらの症状が毎月、日常生活に支障をきたす場合、PMSと診断されることがあります。 なかでも感情の浮き沈みが特に強い場合は「月経前不快気分障害(PMDD)」と呼ばれ、より専門的な対応が必要になることもあります。
更年期障害
日本人女性の平均的な閉経年齢は約50歳で、閉経の前後5年間を「更年期」と呼びます。 この時期に見られる体調の変化のうち、他の病気によるものではない症状を「更年期症状」といい、その中でも、症状が強く、日常生活に支障をきたす場合は「更年期障害」とされます。 主な原因は、女性ホルモン(エストロゲン)の急激な減少に加え、年齢による身体の変化、心の状態、人間関係や社会的な環境などが関係していると考えられています。 治療にあたっては、問診を行い、生活習慣の見直しや心理的なサポートを中心としたケアを進めていきます。 症状の改善が見られない場合には、ホルモン補充療法(HRT)、漢方薬、抗うつ薬などの向精神薬など、症状に応じて薬物療法を行う場合もあります。
避妊
- 経口避妊薬(OC)
- 欧米に比べるとまだ普及率は低いものの、最近では月経困難症への保険適用も進み、徐々に利用が広がっています。
低用量ピルは、正しく服用すれば99%以上の高い避妊効果があり、他の避妊法と比べ確実性が高いとされています。
副作用には、頭痛、吐き気、不正出血などがあります。これらは服用開始初期に見られますが、自然とおさまることがほとんどです。ただし、非常にまれではありますが「静脈血栓塞栓症」という重い副作用が起こる場合があります。服用開始後3か月以内に起こりやすく、喫煙者・肥満の方・高齢の方ではリスクが高くなる傾向があります。
- 緊急避妊(アフターピル)
- 避妊に失敗した後、72時間以内(できるだけ早く)に服用することで、排卵を遅らせたり、子宮内膜の状態を変えたりして、妊娠を防ぐ働きがあります。ただし、100%の避妊効果があるわけではありません。服用後、数日して少量の出血があることがありますが、これは一時的な反応です。次の月経が通常より遅れることがありますが、2週間以上遅れる場合は妊娠の可能性もあるため、早めに受診してください。
副作用として、一時的に吐き気や頭痛などの症状が出ることがあります。服用後4時間以内に嘔吐してしまった場合、薬の効果が十分に得られない可能性があるため、必要に応じて吐き気止めを処方することも可能です。